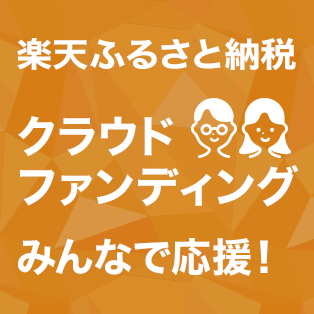老舗の四代目がつないだ森・文化・工藝
日本文化のひとつである国産漆が危機に瀕している。そんな国産漆文化を次世代に継承するため、京都の老舗四代目がたどり着いたのが、サーフィン、スケボー。堤淺吉漆店の堤卓也さんに話を聞いた。
漆とは? 一万年以上もの歴史を持つ素材の魅力
漆とは、ウルシの木からとれる樹液のこと。古くは縄文時代から、矢じりや土器の接着剤、あるいは装身具の塗料として使われ、近代以降は主に漆器や仏壇仏具、寺社仏閣等の文化財の修復などに使われてきた。熱や酸、アルカリに強く、腐敗防止や防虫効果もあるとされる。水分をもったまま硬化するので人肌になじみやすく、使うほどに光沢を増す美しい天然素材だ。


堤卓也(つつみ・たくや)さんは、京都で明治42(1909)年に創業した漆屋「堤淺吉漆店」の四代目。2004年に家業に従事してすぐ、ほんの軽い気持ちで、趣味で楽しんでいたスケートボードに漆を塗ったという。
「好きなものに漆を塗ってみたかったんですよね。スケートボードなら木製だし、簡単に塗れると思って。木に漆が良い感じに染み込んで、味のあるムラになり、カッコ良くなりました」


その頃は、漆塗りのスケートボードで何かを伝えたいという思いはなかった。しかし仕事を続けるうち、漆業界の現状を知り、危機感を募らせていったという。
「漆掻き(漆採取)職人さんたちの多くが70〜80代で、50〜60代がほとんどいないんです。もうあと5年で引退だ、なんて話を聞いているうちに、出会った職人さんが亡くなったりして。それに、僕が生まれた頃は国内で毎年500トンも漆が使われていたのに、この頃になると50トンにまで減少していて、昨年はついに30トンになりました。このままだと本当に漆の文化が消えてしまうと感じました」
こうした現状をなんとかしようとして、素材や職人の魅力を伝えるために冊子や動画をつくったり、大学などで講義をしたりして漆の魅力を伝える活動に力を入れはじめた。それなりの反響があったが、盛り上がっているのは工藝関係者だけ。これでは何も変わらない、工藝の枠を超えて伝えなければいけないのだと気づいた。
プロサーファーたちが認める、漆塗りのサーフボード
そこで堤さんが挑戦したのが、漆を使ったサーフボードづくりだ。
「世界的な木製のサーフボード・クラフトマンであるトム・ウェグナーさんにずっと憧れていて、いつか漆塗りのサーフボードをつくりたいと思っていました。古代ハワイアンが乗っていた木製サーフボード“アライア”を現代によみがえらせたトムさん。世界的にも有名なシェイパー(サーフボードを削る職人)で会えるはずもないと思っていたけれど、SHIN&CO.の青木さんの協力でトムさんにコンタクトを取ってもらって、説明してみたんです。漆とはこういうもので、一枚板でサーフボードをつくり、こういうことを伝えていきたいんだと。そうしたら『すごい! やろう!』という話になって、漆に関心を寄せてくれたんです。そして、一緒に漆塗の“アライア”を製作することになったんです」
実際、漆と木製サーフボードの相性は良かった。漆を塗った場合とそうでない場合とでは、滑走性能が段違いなのだという。
「漆を塗ったボードを水から出すと、水がひとつの塊になって流れていくんです。撥水性があるから相性は良いはずだと思っていたけれど、ここまで効果があるとは、正直驚きでした」
堤さんが海外に出向くと、現地のプロサーファーたちはその性能に大喜びし、またサステナビリティの観点からも絶賛したという。以後、トム・ウェグナーさんがつくるサーフボードには塗料のひとつとして漆が使われるようになった。


こうしてアメリカやオーストラリアのプロサーファーたちが漆塗りのサーフボードに関心を持ち、漆の魅力が、国や人種、ジャンルを超えて伝わるようになった。現在はサーフィンだけでなくBMXなど、エクストリームスポーツの領域で徐々に漆の活用がはじまっている。
人と森を工藝でつなぐ
このような試みにも、はじめは反対意見があった。漆は漆器や仏具に塗るもの、というイメージを抱いていた人は、当初「足で踏んだり、海に入れたりするものに塗るの?」と眉をひそめたという。
「工藝とサーフィンが離れているからそう感じるんですよね。自然素材を使った人の手によるモノづくりである工藝と、海の中で体一つでそのパワーを感じて楽しむサーフィン。共に自然の美しさを感じ、自然のどうにもならない力の前に畏敬の念を生みだすものだと思います。人が本来自然と向き合ってきたカタチだと思うんです。大量生産、大量消費の時代背景の中で見えなくなってきたモノづくりの裏側や、素材や素材を育てる地域への敬意は逆に工藝+サーフィンを通して感じることができるはずです。『漆サーフィン』は国を超えてその価値を共有できると感じています」
そもそも工藝とは自然からできたものであり、もっと言えばそもそも人は森からたくさんのものをもらって生きてきた。それなのに、現在は自然から離れてしまっているものがたくさんある。そうしたものを工藝でつなげないかと堤さんは考えているという。たとえば、京都は工藝・文化の街なので、それを支えてきた森を守ることからはじめなければいけないのではないか。そのような思いから、2019年に共同代表の松山幸子さんと一般社団法人パースペクティブを立ち上げ、京都・京北地区でウルシの木の植栽をはじめた。現在は100本のウルシの木が植えられており、誰でも自由に散策できる。

京北をウルシの産地にしたいわけではない。モノづくりの源流が自然にあることに立ち返り、植えるところから使うところまでの循環を感じられる場にしたいのだという。
「世の中の人が森や木、地域のこと、地球のことを考えられるきっかけにしたいんです。それはきっと、他人や自分を大切にすることにもつながると思うから」
サーフボードやスケートボードをきっかけに漆の魅力を広く発信し、またそれをきっかけに、人と森の関わり方を変えようとしている。老舗漆屋の4代目は、伝統工藝を守り発展させるだけでなく、人々が心地良く生きられる世界を未来につなげようとしている。