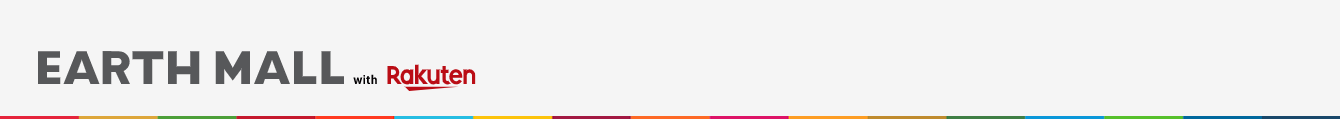- 楽天市場トップ >
- EARTH MALL >
- 読みもの >
- 読みもの >
- 愛媛の旅で出会った、サステナブルなものづくり。
2023/1/16更新
愛媛の旅で出会った、サステナブルなものづくり。
瀬戸内海に面した四国・愛媛県は穏やかな気候と自然に恵まれていて、山海の幸に恵まれた食文化、歴史を感じるレトロな街並み、流れているゆるやかな時間、人のあたたかさや優しさがじんわり心に沁み入ります。EARTH MALL(アースモール)編集部は、そんな愛媛の魅力をさらに深掘りするために、クリエイターとサステナブルなものづくりをする人たちを訪ね、旅をしました。3つの旅を通して出会ったもの、人、文化の魅力 をお届けします。
砥部焼のルーツと未来に繋ぐためのアクション。
白磁の肌に呉須の絵模様が描かれた、手作りの良さが色濃い砥部焼。
ぽってりとした厚手の形は、暮らしによく馴染み、食卓にあたたかさを添えます。砥部焼のルーツと未来への展望を学ぶべく、ブランディングディレクターの行方ひさこさんと旅をしました。
砥部焼と一口に言っても、現在、砥部町には100軒余りの窯元が存在し、伝統を守り続ける窯や新たな表現を探る窯など、様々なスタイルが存在するという。今回は、砥部焼に対する熱い想いを持っている方、未来に残すためにチャレンジしている方々の元を訪れ、“砥部焼のいま”を知る旅に出かけた。

愛媛県の中央に位置する砥部町。高峰に囲まれた山間地域でもある。ところどころに窯元がひっそりと点在している。
1955年に砥部焼の道に進み研鑽を積む中で、海外でも陶芸を指導。砥部焼にチャレンジする次世代につなぐために尽力してきた「八瑞窯」の白潟八洲彦さん。
砥部町五本松出身の白潟さんは御年83歳。砥部焼について分からないことがあったら白潟さんに聞きにいく人も多いという。

“大物づくり”にチャレンジし続けてきた白潟さん。今も、試行錯誤しながら作品づくりに挑む。

松山空港ビルの新築を記念して建てられたモニュメント「えひめ三美神」。白潟八洲彦さんが手がけた10m〜8mの大作。壺を串刺しにしたデザイン。絵付けは身の回りの人たちに手伝ってもらい仕上げた。空や雲と自然に溶け込む様が美しい。
“大物づくり”の名工である白潟さんの代表作のひとつに、「えひめ三美神」がある。長い時間をかけて培ってきた技術と経験によって生み出された、のびやかさと健やかな美しさが宿ったモニュメントだ。
焼き物に専念できるのは、砥部に砥石があるから。
白潟さんは、窯業原料のルーツは、“地球中心部のマグマ”であると考え、常に自然を崇拝する気持ちを心に宿し、活動している。自分が焼き物に専念できるのは砥部が自然豊かな土地に砥石が存在するからだ、と。さらに、砥部にある砥石についても教えてくれた。


「砥部の陶石には『灰色安山岩陶石』『黒雲母安山岩陶石』『変質流紋岩陶石』の3種があります。石を掘ってくれる職人が丁寧な仕事をし続けてくれていることで、僕らは焼き物を作ることができる。白さが際立ったものが特筆していい石だと思います。砥部焼全体の埋蔵量を考えると、あと何千年か分は、作ることができるのでは、と思います。砥部焼という看板を背負って、焼き物をやっている我々にとっては、有難い限り」
石を眺めながらものづくりの話をしているときの白潟さんの眼は、少年のようにキラキラと輝いていて、尽きることのない創作意欲が全身に漲っている。そんな白潟さんを慕い、コラボレーションをしているのが「白青」(Shiro Ao)の岡部修三さんだ。砥部焼の産業そのものが進化する仕組みを考えながら活動を続けている。そうした新たな取り組みを進めるうちに、砥部町にある石について、二人で話合う機会が増えたという。

行方さん、白潟さん、岡部さんと採石場へ。かつては、20〜30箇所の鉱山から採掘されていた砥石だが、現在採掘されている場所は、一箇所のみ。
「白潟さんとのコラボレーションを通じて、砥部焼について深くお話する機会がなければ、“砥部で砥石が取れる”という意義について、意識することはなかったと思います。当然のことですが、1度、循環を止めてしまうと産業そのものが衰退してしまい、戻すことは難しい。そうしたことを鑑みて、今ある資源を大切に活かさなくてはと思い、非営利な活動も始めました」と岡部さんは語る。
伝統工芸である砥部焼を現代で“前進”させるために。
岡部さんは東京で「upsetters architects」という建築設計事務所を主宰していて、建築的な視点で「社会に何ができるのか」を長い時間をかけて、考え続けている人だ。そうした活動の一環として、「白青」では、伝統工芸である砥部焼を理解し、持続可能な産業としての基盤を再構築するために現在抱えている課題のリサーチを続け、俯瞰的なアプローチで一つひとつの仕事に対して丁寧に取り組んでいる。
「よくある、窯元とデザイナーがコラボレーションし、デザインしたものを作って売るだけの一過性の取り組みにはしたくはないと思って臨んでいます。砥部焼の産業自体が進化できるように、砥部焼協同組合の集まりに参加したり、作家や職人の方と密にコミュニケーションを取ったり、砥部にいる人たちと一緒になって、砥部焼を前進させたいと考えています。砥部町は僕の地元なのですが、月に1回は必ず帰り、現地にいる方と交流しながらプロジェクトを進めています」


「呉須(ごす)を巻く」作業を始め「白青」と多く協業する「大西陶芸」の大西先さんと。「一定の呉須の濃さとクオリティを保つため、熟練の職人に担当してもらっています」と大西さん。
また、「白青」のプロジェクトでは、いろんな窯元に仕事を依頼しているという。
「できる限り多くの職人と仕事を分業できるのが理想的。実際に、そうしたことを実現するのは、簡単なことではないですが、ゆっくりでも実現できたら、と考えています。最近は、『白青』を活動ベースとして、ほかのプロジェクトの特注の砥部焼の制作にも取り組んでいます。『白青』の商品は定番シリーズに特化して作っているのですが、新たにプロダクトを増やすことよりも、砥部焼に魅力を感じてくれた人たちと一緒にプロジェクトを展開する方が、未来へのアクションとして発展性があるように思っています。そうした取り組みをすることで、砥部焼の魅力を発信していきたいですね」

軽くて持ち運びやすい「白青」の大鉢。呉須と呼ばれるコバルトブルーの顔料を太縞で巻いた。ほんのり青みがかかった白磁と呉須のコントラストが美しく、光が反射したときの見え方も綺麗。丈夫なつくりで壊れにくいという利点もある。
“砥部焼の普遍性”をデザインに落とし込む。
見た目にも安心感のある形でありながら、手にしたときに重さを感じず、身体への負担が少ない。その理由は、計算し尽くされた緻密なデザインにある。
「形に関しては、砥部の50〜80窯くらいの形を網羅的にトレースして、そこから標準的と言える形状を見出して、砥部焼の普遍性を求めるようにデザインをしました。その上で手に持った際に軽く感じるように調整しています。客観的に見たときの“砥部焼っぽさ”と現代の生活に馴染むモダンに感じるデザインのバランスを意識しました」

くらわんか碗、平皿、鉢、蕎麦猪口、湯飲みをスタンダードシリーズとして展開。洋食器のような考え方でサイズ展開がされている。「スタンダードシリーズに絞ってプロジェクトを展開されているスタイルや職人さんへの仕事の配分を考えてものづくりされているサステナブルな指針が素敵だと思います」と行方さん。

ロクロを回しながら、ひと筆で呉須を巻く、シンプルな技法を採用。至近距離で眺めると、筆による独特の手仕事の味わいを確認できる。豆皿〜特大皿までをスタッキングしたときの整った見え方も様になる。
「白青」のプロダクトを実際に見て、触れることができるのは、コンセプトショップ「WIHITE/BLUE」だ。パン屋、古本屋、コーヒーショップなど、味わい深い個人店が立ち並ぶ「柳井町商店街」という名のレトロなストリートにある。
「基本的に作っている商品は、全部置いています。また、この店は事務所的な役割もあって。この場所を選んだのは、何より、砥部町までのアクセスの良さ。
すぐ近くにはバス停があり、砥部町に行きやすいんです。ここを起点にすれば、いろいろな窯元を回ることができると思いますし、『砥部焼に関わりたい』と声をかけてもらったときは、ノウハウを伝えたり、職人の方を繋いだりする場所にしたい、と考えています。お客さまは、観光客の方や砥部焼そのものに興味を持ってくださる方も多く、「WIHITE/BLUE」が砥部焼、ひいては砥部町の入り口になってくれたらいいな、と考えています」

INFORMATION
WHITE/BLUE 住所:愛媛県松山市柳井町1-2-10 1F 営:12:00-18:00(アポイントメント制) HP:https://white-blue.jp E-mail:info@white-blue.jp
そして、旅の終わりには「白青」の岡部さんが関る、道後にあるギャラリーショップ「Mustakivi」(ムスタキビ)を訪れることに。「Marimekko」(マリメッコ)を代表するデザイナーとして活躍し、フィンランドで50年ほど暮らしていたという、デザイナー/陶芸家の石本藤雄さんが、2年ほど前に地元、愛媛県に戻り、自然と対話しながら、ものづくりを楽しんでいる。この場所では、暮らしを豊かにしてくれるアート、うつわ、雑貨に出合うことができる。併設の空間は、石本さんのアトリエになっている。

ディレクターであり創業者の黒川栄作さんが、石本さんの過去・現在・未来を地元、愛媛で伝えることを目的に「Mustakivi」がスタートした。

「僕の先祖は、良質な砥石が採れる砥石山の麓に住まいを構えていたようなんです。苗字が石本なのも、おそらくそうしたことが関係しているかと」。朗らかな笑みを浮かべ、自身のルーツについて語る石本藤雄さん。
フィンランドから地元、松山へ。
自然と向き合うことで生まれる作品。
50年ぶりに愛媛に戻ってきたという石本さん。改めて自身のルーツに向き合う日々を過ごす中で、作品づくりに何か影響を感じたことはあるのだろうか。
「2022年7月より『蕾-つぼみ-』という作品展を開催しました。これから花ひらく前の蕾を表現したものです。植物に対して、すごく興味があるし、“懐かしい”という感情を抱くことも多いです。年齢を重ねたいま、幼いときの記憶が蘇ってくるんです。僕は、幼い頃に木登りをよくやっていて、庭にある泰山木に登ったりしていました。そのときは、咲いていた花を覚えておらず、10年前くらいに東京に戻って来たときに、泰山木を公園で見かけて、こういう花だったのか、と見惚れたことがあって。今回の、作品展では、その花びらを取り入れた作品も展示しました。それと、僕が松山に帰ってきたときに、街路樹の花が一面ピンクになっている季節がとても印象に残っています。フィンランドは、白っぽい花が多いので、その色彩がとても新鮮で、強烈に子供の頃を思い出しました。そういった、僕が見た景色が作品に投影されることはあると思います」

石本さんが手がけた、さまざまな形やフォルムの「蕾」。花が咲き誇る前の蕾の状態が、未来へのイメージを膨らませてくれる。
また、石本さんにとっての「砥部焼」とはどういった存在なのだろうか。
「実家にあったうつわは、砥部焼がほとんど。呉須を筆で巻いたものや型絵染付のものが当たり前に存在していました。改めて、砥部焼というものは、なんなのだろう? と問い直したときに、自分は、“砥部の砥石で作られた磁器”ということだと思っています。絵付けや釉薬の表現よりも、その事実が大事だと、僕は思います」

石本さんが陶芸を学び始めた頃にロクロで制作した形をベースに作ったゴブレット。長年、温めていたという高台をつけるアイデアを「Mustakivi」で実現。画用紙を切り貼りして模型を制作し、カップと高台のプロポーションを定めた。

ゴブレットのシリーズ名は「ONNEA」。フィンランド語で「おめでとう、お幸せに」という意味を込めて、石本さんが命名。カラーバリエーションを含めると全部で20種ほどある。
「Mustakivi」のゴブレットを眺めた行方さんは、「和洋折衷の空間にも合いそう」と第一印象を語ってくれた。
「例えば、数寄屋造りのシンプルな空間に、北欧家具を置いたりしているようなイメージによく似合うというか。釉薬の色のチョイスがとても綺麗で絶妙で。和と洋のどちらにも偏りすぎない、デザインがとても素敵だと感じました。今回、砥部焼の歴史といまを知る旅を経験させてもらったことで、砥部には、砥石が存在していることがとても恵まれたことなのだと、改めて感じています。ほかの産地を訪れたときに、これからの時代、純粋に日本製のものが作れなくなるのでは、という危機感を感じていたので。また、砥部焼自体、“中量生産”で無駄に作り過ぎて在庫を抱える、という問題が発生していないと思われる状況が、とてもいいことだと思っています。私は企画展を開催することもあるのですが、そういった場でも砥部焼の魅力を伝えて行けたら、と思っています」

INFORMATION
住所: 愛媛県松山市道後湯月町3-4 上人坂テラス TEL:089-993-7497 営:11:00-17:00 休:月/火/水/木 HP:https://mustakivi.jp/
Photo by: Tetsuya Ito Edit & Text by : Seika Yajima
Keywords
読みもの
カテゴリ一覧
注目のキーワード
- SUSTAINABLE JOURNEY
- WE FOUND EHIME
- 「これからの未来」への話
- みんなのサステナブル
- アウトドア
- アップサイクル
- アニマルウェルフェア
- インテリア
- エコフレンドリー
- オーガニック
- グルメ
- サステナブルな買いもの入門
- スキンケア
- ファッション
- フェアトレード
- リサイクル
- ヴィーガン
- 国産
- 地域活性
- 暮らし
- 編集部のお買いもの日記
- 脱プラ