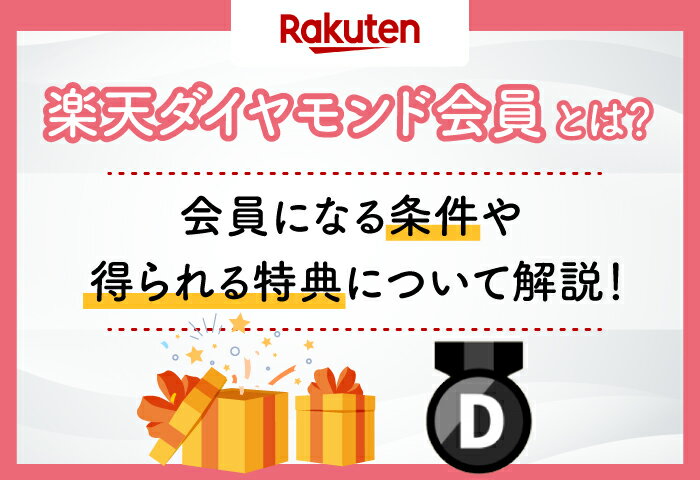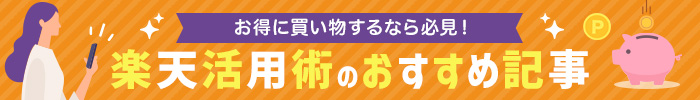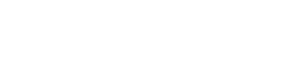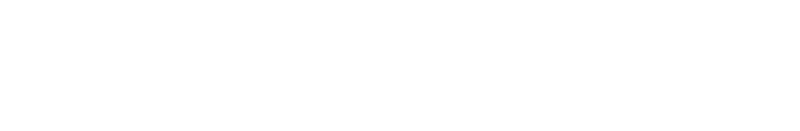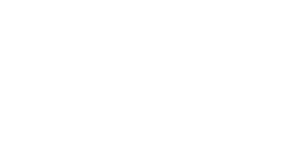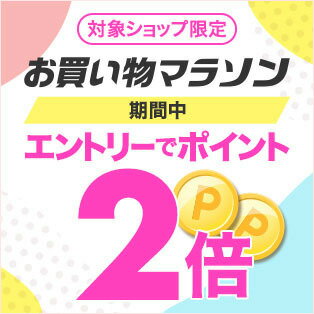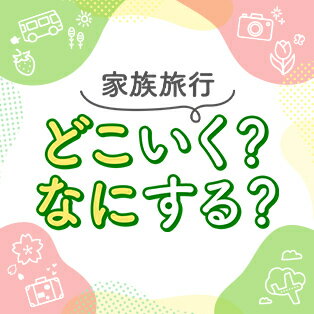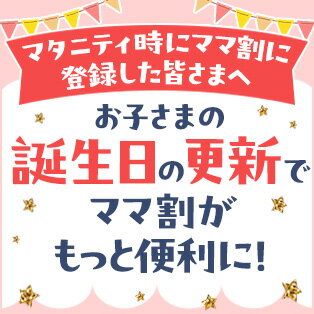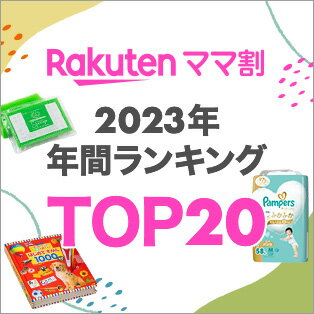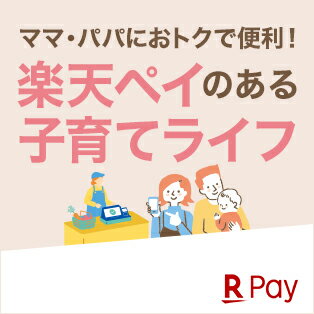夏休みの自由研究のまとめ方を解説!【小学校低学年~高学年】
2023/7/14
夏休みの自由研究を進めていて、まとめ方がわからず困っている方も多いかと思います。この記事では、小学校低学年・高学年それぞれについて、自由研究のまとめ方を解説しています。また発展として、さらによいレポートを書くためのポイントも解説しています。

夏休みの自由研究、研究や観察、調べ物系のテーマに挑戦し、どうまとめればいいか困っている方も多いと思います。そこで、この記事では、夏休みの自由研究の上手なまとめ方をご紹介します!
低学年・中学年・高学年と、学年別に自由研究のまとめ方のポイントもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
【全学年共通】自由研究のまとめに含めるべき項目一覧
自由研究は、模造紙、レポート用紙やノート、スケッチブックなどにまとめていくことになります。何にまとめるにせよ、自由研究をまとめるときは、はじめに以下の項目を記載しましょう。
<自由研究の冒頭に記載する項目>
・タイトル
・学年・クラス
・氏名
※書き方に指示がある場合はそれに従いましょう。
研究内容のまとめに入れる項目は、自由研究のテーマが【観察系】【実験系】【調べ物系】のいずれかによって変わってきます。以下に、それぞれのまとめ方をご紹介します。
観察系の場合
観察系の自由研究は小学生の定番。低学年でも取り組みやすいテーマですよね。
観察系の自由研究の場合には、以下のような項目を設定してまとめていきましょう。
観察系の自由研究では、写真やイラストを使用してまとめていきましょう。日付もしくは、「発芽〇日目」などと経過がわかる日数を記載し、気付いたことを書いていきます。
最後には観察を通して気付いたことや感想をまとめましょう。
【観察系自由研究のテーマ例】
・虫の観察・調査(カブトムシ、アリの巣観察など)
・植物の観察・調査(アサガオ、ミニトマト、ひまわり、しいたけ、水草など)
・動物の観察・調査(釣った魚の観察など)
・天体の観察・調査
実験系の場合
実験系の自由研究には、大シャボン玉づくりの実験や、身近なものから電池をつくる実験、炭酸水づくりの実験などがあります。
実験系の自由研究をする際は、以下のような項目を立ててまとめていくといいでしょう。
実験系の自由研究では、結果の考察で今後の課題や、自分なりの考えを示すことができるとよりよいレポートになります。
高学年の場合は、「次はこういう条件で実験してみたい」など、結果を踏まえたネクストアクションを書いてもいいでしょう。
【実験系自由研究のテーマ例】
・科学実験
・物作りや体験教室(石鹸づくり、キャンドルづくり、スライムづくりなど)
・料理やお菓子づくり

調べ物の場合
歴史や文化、気になった物や施設など、調べ物系の自由研究では、以下のような項目を立ててまとめていくといいでしょう。
中~高学年の場合は、単に調べたことをまとめるのではなく、予想や仮説を立てたうえで調べ、結果と予想の差異や、さらに調べてみたいことなどを記載すると、より発展的な研究になります。
【調べ物系自由研究のテーマ例】
・歴史に関連する調査
・工場、博物館などの見学
・地理に関連する調査
・住んでいる地域に関する調査
・外国に関連する調査
・SDGs、ジェンダーなど社会問題に関する調査
自由研究は何にまとめる?3種類紹介!
次に、自由研究のまとめを記載する用紙の選び方をご紹介します。模造紙、ノート、スケッチブックなど、用紙によってメリット・デメリットがあるため、自由研究のテーマから適した用紙を選びましょう。
模造紙:新聞風にまとめられる!
模造紙は、実験系や調べもの系のまとめに適しています。
<模造紙のメリット>
・一覧で内容を確認できるため見る人がわかりやすい
・新聞風にまとめられる
・インパクトがある
<模造紙のデメリット>
・レイアウトが大変
・内容が多いと1枚でまとめられない
模造紙にまとめる方法は、一覧で見やすいため、研究の内容をわかりやすく伝えることができるのがメリットです。ただし、1枚にまとめなければならないためレイアウトが難しく、文字数も気にする必要があります。
模造紙にまとめる場合は、レイアウトを決めてから一度えんぴつで下書きをし、消えないマジックなどで清書をして仕上げていきましょう。
ノート・レポート用紙:観察系のまとめに最適!
ノート・レポート用紙は観察系のまとめに適しています。
<ノート・レポート用紙のメリット>
・内容に応じて枚数を調整できる
・書き直しが楽
・ガイドラインやマスがあるため字を書きやすい
<ノート・レポート用紙のデメリット>
・模造紙と比べるとインパクトに欠ける
・大勢の前での発表に不向き
ノート・レポート用紙は手軽に用意でき、失敗しても書き直しがしやすいのがメリットです。字のバランスをとるのが難しい低学年でも、授業で使い慣れた方眼ノートであればきれいに字を書くことができます。
実験用の方眼ノートや観察用のレポート用紙なども市販されているため、用途に合ったものを選ぶとまとめやすいでしょう。
スケッチブック:図やイラストが使いやすい!
スケッチブックは観察系や実験系の自由研究で、図やイラストを書き込みたい場合に適しています。
<スケッチブックのメリット>
・紙が厚いため色ペンや絵具などを使える
・書き方次第でインパクトを出せる
<スケッチブックのデメリット>
・ガイドラインがないため字のバランスをとりにくい
スケッチブックは紙が厚く、ノートよりも自由な表現ができるため、よりインパクトのあるまとめをつくることができます。ただし、模造紙と同じく自分でレイアウトや文字の大きさを調整する必要があります。
見やすくまとめるために、「見出しの文字を大きく書く」「目立つ色を使う」など工夫してみましょう。

自由研究のまとめ方のポイントは?
ここからは、よりよい自由研究にするためのまとめ方のポイントを4つご紹介します。
「自分の気付いたことや、知ってほしいことが伝わりやすい自由研究にしたい」という子には、以下のポイントを意識するようにアドバイスしてあげてください。
図やイラストを多く使う
自由研究のまとめでは、図やイラスト、写真を多く使うようにしましょう。そうすることで、視覚的に見やすくなり、見た人に研究の内容が伝わりやすくなります。
自由研究は人に見てもらうことが前提のため、初めて見る人を惹きつけるようなまとめ方が大切です。マジックなどで太くはっきり書くこと、目立たせたい部分に色を付けることも見やすくまとめるコツです。

実験・観察中の気づきや疑問をまとめる
自由研究には、事前の予想だけでなく、研究中に「気付いたこと」や「疑問に思ったこと」を入れてみましょう。結果で確認するポイントがわかりやすくなるので、考察もしやすくなり、まとめるときに役立ちます。
実験や観察中、想定していなかった課題や疑問が生じたときはメモをとっておくのがおすすめです。
高学年の場合は、その疑問から自分なりの考察や今後の課題などをまとめられるとよいでしょう。
下書きをしてからまとめる
自由研究を上手にまとめるコツは、「下書きをすること」です。
書くべき内容が多い自由研究においては、いきなりレポートやスケッチをはじめてしまうと、まとめづらくなったり、見づらくなったりする可能性があります。
見やすくするためには、レイアウトやスペースにあった文字数で書くことが大切。最初に下書きしてから書くことで、きれいにまとめることができます。
わかったことと感想をしっかり区別する
小学生の自由研究では、「わかったこと」と「感想」が一緒になってしまうことが多いです。わかったことと感想を分けることで、読み手にも研究結果がわかりやすくなります。
低学年だとまだ区別が難しいですが、中学年~高学年になったらあらかじめ意識しておけるとよいでしょう。
また、より詳しく自由研究のテーマ選びや、楽しく自由研究を行うコツが知りたい方は、「【自由研究】コツやテーマの決め方を元教諭の中尾さんに聞いてみた」の記事も併せてご覧ください。元小学校教諭の中尾恵美さんに聞いた、自由研究の取り組み方をご紹介しています。
低学年(小学校1・2年生)向け自由研究のコツ
低学年の場合、まだ自分だけでまとめるのは難しいため、親の手助けが必要です。「テーマ決め」「何にまとめるか(用紙)」「まとめに入れる項目」は親がサポートしてあげましょう。
テーマはインターネットなどを参考にしつつ、子どもが好きなことや関心があること、疑問に思っていることなどから決めていくといいでしょう。低学年のうちは工作系が人気ですが、虫や植物の観察も興味をもって取り組みやすいテーマです。
まとめ方は、低学年では絵日記のように観察記録を書いたり、模造紙や画用紙1枚にまとめたりする方法が書きやすくおすすめです。まとめる作業は大変ですが、完成した作品をみんなに見てもらえたときには大きな自信につながりますよ。
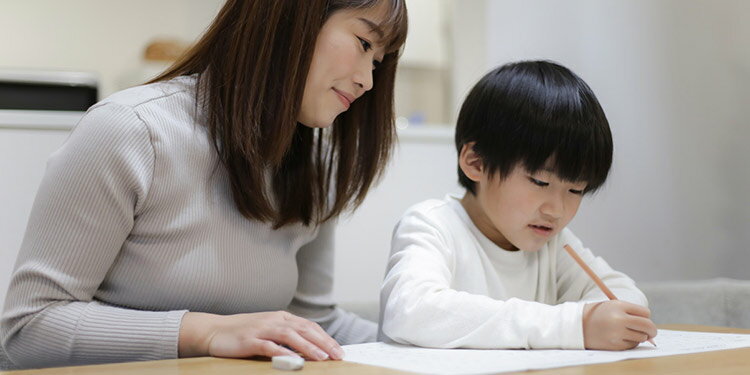
中学年(小学校3・4年生)向け自由研究のコツ
中学年になると、自分でテーマを絞れるようになってくるため、「なぜそのテーマを選んだのか」も、まとめに記載するといいでしょう。
「自分なりの予想」や「結果からの考察」もまとめの項目として入れられると、低学年から一歩進んだ自由研究になります。
まとめの際は文字数も増えるため、画用紙や模造紙にまとめたい場合は、数枚に分けてもいいでしょう。
高学年(小学校5・6年生)向け自由研究のコツ
高学年になると内容が高度になるため、まとめの記述量も増える傾向にあります。そのため、テーマに応じたまとめの用紙選びやレイアウト・見せ方の工夫が大切です。
写真を多く使うものは模造紙、実験など文字量が多くなる場合はレポート用紙など、研究内容に合ったまとめ方を事前に考えておきましょう。
高学年の自由研究のまとめでは、「仮説・予想」や「結果からの考察」に加え、「結果を踏まえた今後の課題」や「補足情報」なども記載できるといいでしょう。時間があれば課題を受けて発展研究まで挑戦してみると、より高度な内容となりますよ。
使えるワークシート付!夏休み自由研究&読書感想文 進め方ガイド
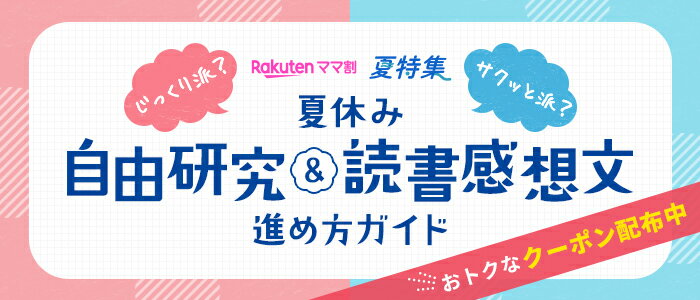
毎年頭を悩ませる夏休みの宿題。特に自由研究と読書感想文は子どもだけではなかなか進まず、親も疲弊しちゃいますよね。そんなお悩みについて楽天ママ割がお答えする今回の企画。元教師が教える親の関り方や効率的な進め方や宿題に使える楽天サービス、まとめに使えるワークシートなどコンテンツが盛りだくさんです。
子育てに役立つサンプルボックスを毎月プレゼント中!無料の楽天ママ割に登録を♪
自由研究は先生や友だちに見せることが前提のため、まとめ方がとても重要です。文字だけでなく、イラストや写真などを使いながら、はじめて見る人でもわかりやすい内容にまとめていきましょう。
とくに低学年の場合はまだ自分でまとめることは難しいため、うまくまとめられるようサポートしてあげてくださいね。
さて、子育て中のママやパパを応援する楽天のお得なサービス「楽天ママ割」をご存じですか?
楽天ママ割に無料登録&エントリーすると、「サンプルボックス」が当たるキャンペーンを毎月開催中です。そのほか、ママ割限定のクーポンやポイントキャンペーンなど、お得な特典が満載。登録は無料ですので、ぜひこの機会にチェックしてみてくださいね。
この記事をシェア
関連キーワード
関連記事
-
小学生向け夏休みの自由研究ランキング!おすすめキットも紹介
2023/06/30
-
【小学生向け】 ママ割メンバーアンケート!人気のクリスマスプレゼントを男女・学年別に紹介
2022/11/18
-
小学生の子どもにおすすめの習い事は?楽天ママ割メンバーに聞いてみた!
2023/02/06
人気のキーワード
PICK UP
-
【公式】メリットがいっぱい!楽天経済圏のカンタンな始め方
2024/1/10
-
【公式】楽天ママ割とは?お得な特典から使い方まで全解説
2023/2/24
-
楽天ふるさと納税のやり方は?初心者向けに手続きの流れを解説
2022/12/2
-
楽天ダイヤモンド会員とは?メリット・特典や条件について解説!
2024/1/31
SPECIAL
-
【公式】楽天ママ割とは?お得な特典から使い方まで全解説
2023/2/24
-
楽天ダイヤモンド会員とは?メリット・特典や条件について解説!
2024/1/31
-
保存版!楽天経済圏とは?楽天ポイントでお得に暮らす完全ガイド
2024/1/10