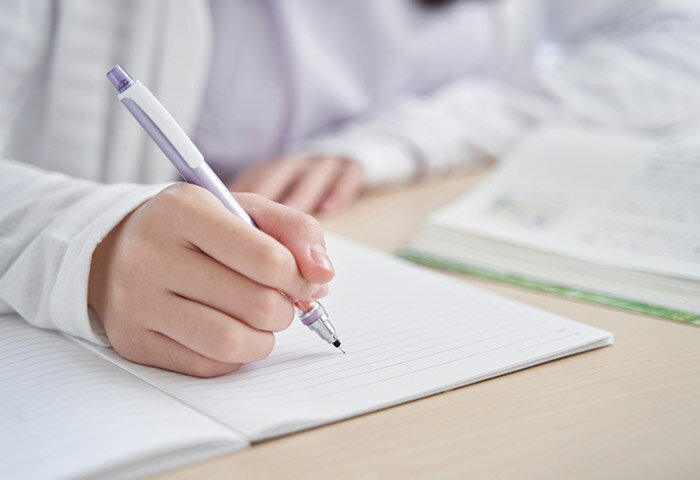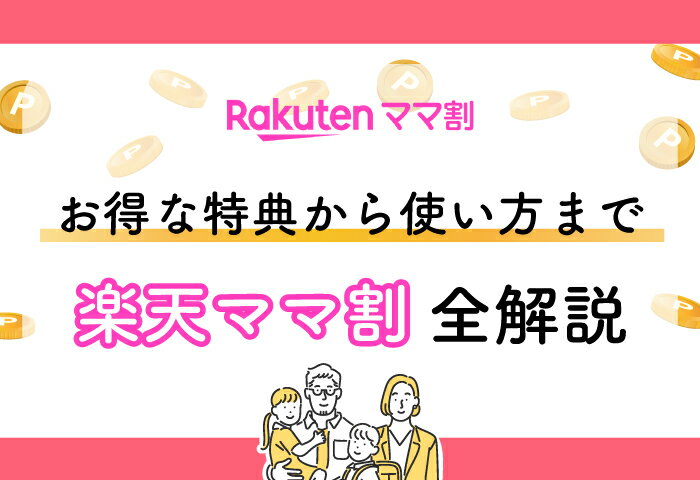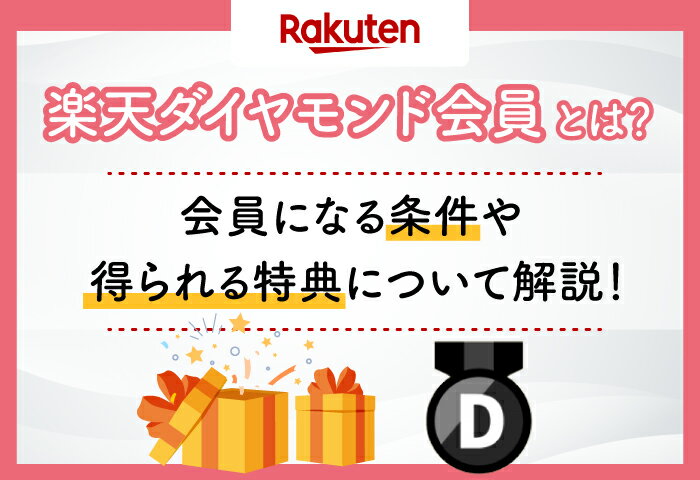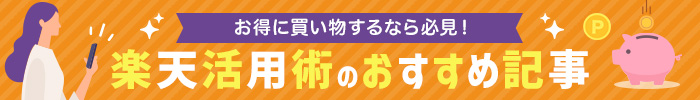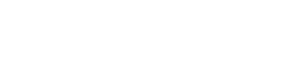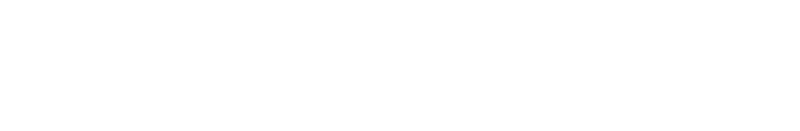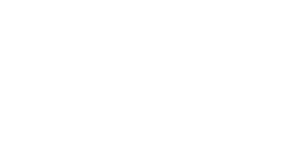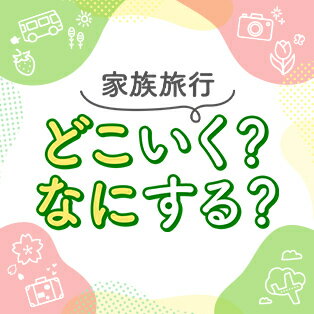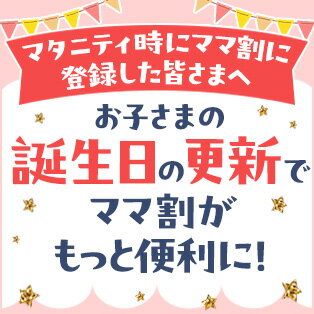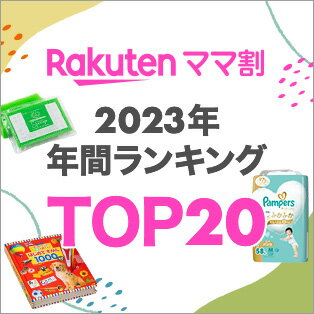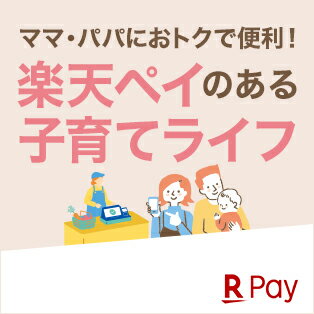小4の壁とは?原因や乗り越えるサポート方法をケース別に解説!
2023/1/30
小4の壁とは、10歳頃の子どもが「放課後の居場所がない」「学校の勉強についていけなくなる」「劣等感を感じるようになる」といった問題に直面することです。この記事では、ケース別に小4の壁を乗り越える方法を解説していますので、参考にしてみてください。
小学4年生は、「勉強についていけない」「学校に行きたくない」などの悩みが増える時期です。「小4の壁」といわれるこの問題を乗り越えるためには、9〜10歳の心の発達や悩みなどをよく理解することが重要!そこでこの記事では、小4の壁の原因や対処方法などを紹介します。

目次
小4の壁とは
「小4の壁」とは、9〜10歳頃の子どもが学習面や人間関係などで困難に直面し、不安や劣等感を抱いてしまう問題のことです。小4の壁ではなく、「9歳の壁」や「10歳の壁」と呼ばれることもあります。
この問題が生じる主な原因は、
・放課後の居場所に関する問題
・10歳頃の精神的な発達によって生じる悩み
・学習面での劣等感
であることが多いです。
小4になると、自分のことを客観的に見られる年齢になり、他者との学力や身体的な発達、環境などの差が目につくことで、子どもが劣等感を抱いたり自己肯定感が下がったりしやすくなるのです。
そのほかの原因については、「小4の壁が起きてしまう原因」の項目で詳しく解説します。
子どもの成長と共に起こりうる問題には、「小1の壁」もあります。これは、保育園のような延長保育がなくなることで、親が働き方を変えざるを得なくなることです。
小1の壁の原因や対処法は、「小一の壁は越えられる?実態から対策まで解説!」の記事で詳しく解説しています。未就学児の子どもがいるママ・パパは参考にしてください。
小4の壁が起きてしまう原因
小4の壁が起きる原因は、精神面や勉強面、家庭環境などさまざまです。その中でも、特に多い原因を5つ紹介します。
学童保育がなくなり居場所が減る
放課後の居場所を確保することは、共働きの家庭にとって大きな課題です。
2015年4月より「子ども・子育て支援新制度」が施行されたことで、学童の対象年齢がおおむね10歳未満から小学6年生まで引き上げられました。
しかし、まだ小学3年生までしか受け入れていない施設が多いのが現状です。また、小学4年生以降の受け入れが可能な施設でも実際の利用者は少なく、子どもが学童に通う友達がいないことを理由に辞めたがることも少なくありません。

授業のレベルが急激に上がる(抽象的概念が増える)
小4は学習内容の難易度が急激に上がり、勉強が苦手な子と得意な子の差が顕著に現れる時期です。
特に数学は分数、理科は電気など、具体的にイメージすることが難しい抽象的概念が必要な授業が増えます。抽象的な思考が成長する時期ではありますが、まだ個人差が大きいためつまずきやすいポイントです。
また、国語は論理的思考を問う問題が増え、これまで以上に読解力などが求められます。
中学受験準備がスタートする
中学受験の勉強は、小学3年生の2月頃から始めるのが一般的です。中学受験に向けて塾に通う子とそうでない子の学力の差が開き、劣等感や不安感を抱くこともあります。
また、中学受験によって親の負担も増えます。「親の受験」ともいわれる小学校受験よりも両親の役割は減るものの、仕事をしながら受験勉強のサポートをするのは容易ではありません。両立が難しく、仕事を辞めてしまう親も一定数いるのが現状です。
客観視する力がつき、他人と比べるようになる
客観視する力がつくことで、「他人から自分がどう思われているか」ということを気にするようになります。他人と自分を比べて、劣等感から自己肯定感が下がることもあるでしょう。
特に繊細な子は、友達や先生からの何気ない言葉や態度に過敏に反応し、精神的に疲れてしまうこともあります。
友人関係でトラブルが増える
小4になると、特定の子と過ごす時間が増え、より明確なグループが確立されます。友人関係が濃く、狭くなることで依存や束縛、同調圧力などが生じ、仲間外れなどのトラブルが発生することも。
令和3年の文部科学省のいじめ調査によると、いじめの認知件数は低学年に比べるとやや減少するものの、小学4年生もまだ高い水準をキープしています。
中間反抗期真っ最中の子どもは親に相談できず、閉鎖的な学校の中で孤独に悩むことも少なくありません。
参考:文部科学省「いじめの現状について 」
中間反抗期について詳しく知りたい方は、「中間反抗期の原因や特徴とは?対処法を生かして乗り越えよう!」 の記事をご覧ください。
小4の壁を乗り越えるためのサポート方法~精神面~
子どもが小4の壁を乗り越えるためには、自己肯定感を上げ、良好な親子関係を築くことがとても大切です。
ではママやパパはどのような方法で子どもの精神面をサポートすれば良いのでしょうか。具体的な対処法を4つ紹介します。
自己理解できるようにサポートする
子どもが自分の得意なこと、苦手なことを理解できるように、サポートしてあげましょう。得意・不得意を自分で理解していれば、人間関係や勉強など、さまざまな場において物事に対処しやすくなります。
ここでポイントになるのが、子どもが自分のことを過小評価・過大評価しすぎないように助言してあげることです。「どうせ自分には無理」と思っているとやる気が起きず、逆に過大評価していると、現実とのギャップを目の当たりにした時にショックを受けて、自己肯定感が下がることが考えられるからです。
例えば勉強であれば子どもが間違えやすい問題や解くのに時間がかかる問題を親が把握する、テストの点数を記録しておくなど、子どもが自己分析できるようにサポートしましょう。
具体的に褒めてあげる
子どもを褒める時は、具体的に褒めましょう。
例えば、「前回間違えた問題を、今回は正解しているね!」「漢字の勉強は苦手だけど、○点も取れてすごい」など、どこが良いのか、なにがすごいのかを具体的に言語化します。
ただ「100点が取れてすごい」と言われるよりも、具体例を出すことで「自分の努力や頑張りを見てくれている」と実感し、自己肯定感を上げることができるのです。

共感して寄り添う
時には、親に反抗的な態度をとることもあるでしょう。しかし、子どもは自分の気持ちを分かってほしい、認めてほしいと思っています。
まずは、子どもが感じている劣等感や不安に対して共感することが大切です。大人でも頭ごなしに正論をぶつけられるよりも、寄り添う姿勢を見せられた方が素直に話を受け入れられますよね。
伝えたいことがある時は親の意見を押し付けず、子どもの気持ちを理解しようとする姿勢を見せましょう。
ほかの子と比較しない
親はつい、他人よりもわが子の劣っているところが目についてしまいます。しかし、「○ちゃんはできるのに」というような声かけは、子どもの劣等感を増幅させるだけです。
子どもとしっかり向き合い、一番の味方になってあげてください。
小4の壁を乗り越えるためのサポート方法~勉強面~
勉強でつまずくと「学校に行きたくない」「自分に自信が持てない」など、日常生活にも支障が出てしまいます。
そうならないために、ママやパパが勉強面でできるサポートを3つ見ていきましょう。
基礎から復習する
小学4年生の学習で特につまずきやすいのが算数です。小学3年生までは、足し算や引き算、九九など、基本的な計算方法をそのまま当てはめれば答えが出る問題がほとんど。一方で小学4年生からは、図形や筆算など、今までに習った数学的要素の中から最適なものを選択し、活用する必要があります。
もし応用問題でつまずいている場合、基礎から学習し直しましょう。類似した問題を解き、どこでつまずいているのか突き止め、復習・反復することで学力を底上げします。
具体的にイメージできるようにサポート
道順を尋ねたときに、口で説明されるよりも、地図と言葉で説明された方が実際の行動をイメージしやすくなりますよね。
もし抽象的な問題につまずいた時は、図やイラストを用いて、問題を可視化してみましょう。視覚にアプローチすることで、理解力がアップするはずです。
具体的にイメージできるようにサポートすれば、徐々に頭の中で問題を整理することができるようになるでしょう。
抽象的な表現に触れる機会を増やす
抽象的な表現に慣れるためには、読書習慣をつけるのがおすすめです。挿絵が無い本は、文章から物語の情景を想像する力が養われます。
まずは短編小説から挑戦し、繰り返し抽象的な表現に触れることで自分や周囲の状況を客観視する力が高まるのではないでしょうか。

ママ・パパが小4の壁を乗り越える方法
子どもが小4になり、さまざまな変化を迎えることに伴い、ママやパパのライフスタイルや働き方も大きく変えなくてはならない可能性があります。
子育てと仕事を両立させるためには、時短勤務などの制度をうまく利用することがポイントです。時短勤務とは、子育てや介護によりフルタイムで働くのが難しい人たちが、勤務時間を原則6時間に短縮できる制度のこと。法律では3歳未満の子どもを育てる従業員が利用できる制度ですが、企業によっては、子育て世代をサポートする独自の時短勤務制度を導入していることもあります。
もし、在籍している会社で子育てとの両立が難しいなら、福利厚生や子育て支援が充実した会社に転職することも視野に入れなければいけません。
放課後や休日は、子どもを塾やプログラミング教室などの習い事に通わせるのもひとつの方法です。学童の代わりになり、親の勉強のサポートの負担も軽減されます。夢中になれる習い事ができれば、精神的に安定する可能性もあるでしょう。
ママやパパにとっても負担が大きい時期ですが、小4の壁は子どもの成長の証でもあります。悩みを抱え込みすぎないようにすることも大切です。
子育てに役立つサンプルボックスを毎月プレゼント中!無料の楽天ママ割に登録を♪
小4の壁は、急激に学習の難易度が上がることや、客観視できる力が付き劣等感を感じることなどによって引き起こされます。子どもの自己肯定感が上がるような褒め方をする、基礎を固めるなど、ママやパパが精神面や勉強面のサポートをして乗り越えましょう。中間反抗期と重なる大変な時期ではありますが、子どもの成長の証でもあるためあまり心配せず長い目で見守ってあげられるといいですね。
最後に、子育て中のママ・パパにおすすめの「楽天ママ割」について紹介します。
楽天ママ割は、妊娠中・子育て中のママやパパがさまざまな特典を受けられるサービスです。無料登録をすることで、限定クーポンをもらえたり、ポイントキャンペーンに参加できたりとお得がいっぱい!さらに、選べるサンプルボックスがあたるキャンペーンも開催しています。
お得に楽天サービスでのお買い物を楽しむために、ぜひ楽天ママ割を一度チェックしてみてください。

この記事をシェア
関連キーワード
関連記事
-
小学生に渡すお小遣いの相場は?渡し方や注意していることを調査!
2022/05/19
-
【元教諭監修】小学生の読書感想文の書き方!便利なまとめ方シートも
2023/06/30
-
学童保育とはどんなところ?特徴や時間、利用料金などを詳しく解説
2021/08/25
人気のキーワード
PICK UP
-
【公式】メリットがいっぱい!楽天経済圏のカンタンな始め方
2024/1/10
-
【公式】楽天ママ割とは?お得な特典から使い方まで全解説
2023/2/24
-
楽天ふるさと納税のやり方は?初心者向けに手続きの流れを解説
2022/12/2
-
楽天ダイヤモンド会員とは?メリット・特典や条件について解説!
2024/1/31
SPECIAL
-
【公式】楽天ママ割とは?お得な特典から使い方まで全解説
2023/2/24
-
楽天ダイヤモンド会員とは?メリット・特典や条件について解説!
2024/1/31
-
保存版!楽天経済圏とは?楽天ポイントでお得に暮らす完全ガイド
2024/1/10